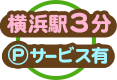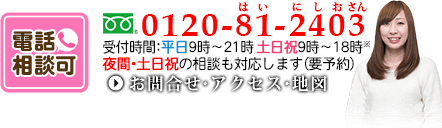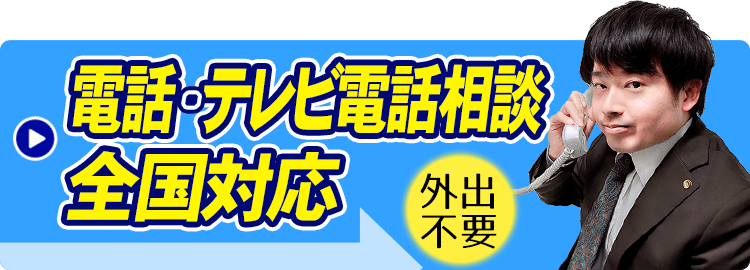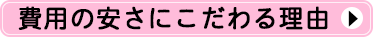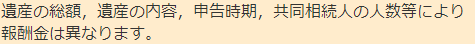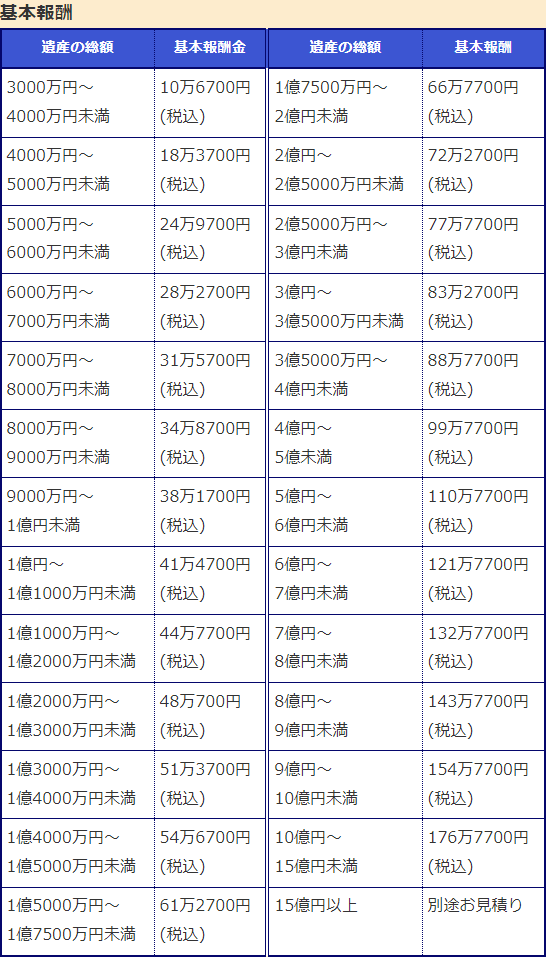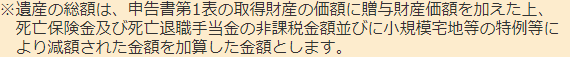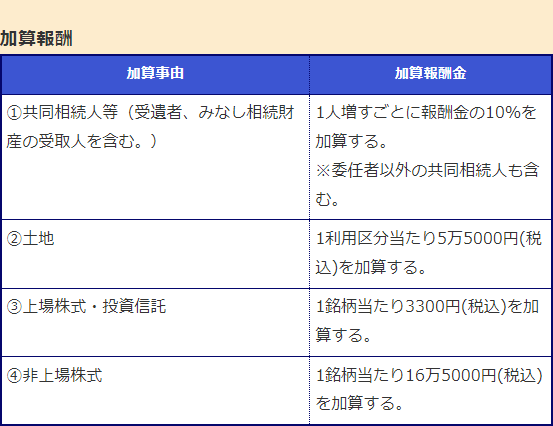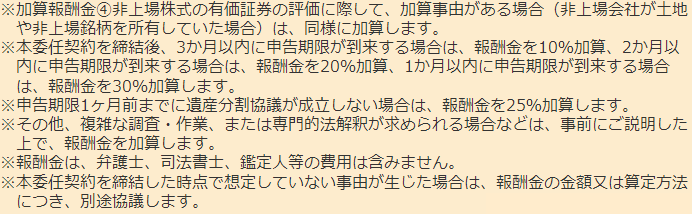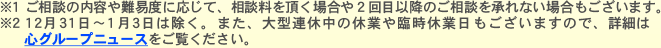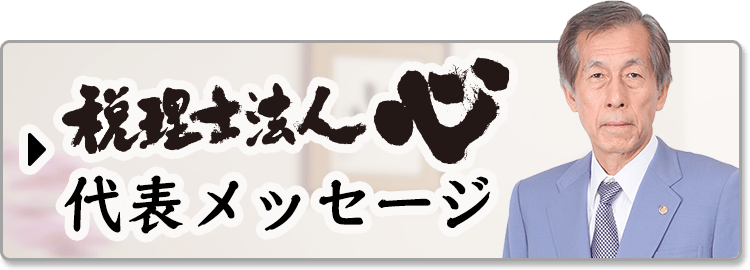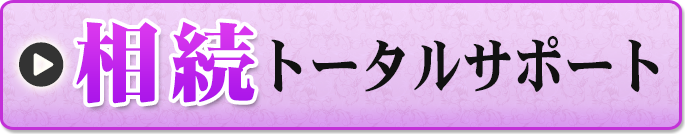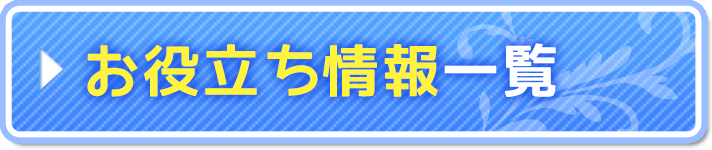「相続税対策」に関するお役立ち情報
不動産を活用した相続税対策のメリット
1 不動産を活用した相続税対策とは
たとえば、現金で1億円を相続すれば、相続税評価額も1億円となります。
他方で不動産を1億円で購入した場合、相続する際の評価額は1億円よりも2~3割程度低くなることが多いです。
理由として、不動産の相続税評価額は、土地は相続税路線価、建物は固定資産税評価額で評価されることが挙げられます。
相続税路線価は公示価格の8割、固定資産税評価額は公示価格の7割が目安となるからです。
そのため、現金で不動産を購入することで、相続税評価額を少なくすることができ、相続税対策となります。
2 不動産を活用した相続税対策の例
⑴ 第三者に対する賃貸
前記1のとおり、不動産の相続税評価額は時価よりも低くなります。
そして第三者に賃貸すると、相続税評価額がさらに低くなります。
具体的には、賃貸物件の土地は、貸家建付地となります。
地域ごとに定められた借地権割合、全国一律30%と定められた借家権割合、空室を加味する賃貸割合を用いて計算することで、自宅用の場合の相続税評価額より低く評価することになります。
⑵ 小規模宅地等の特例
亡くなった方の自宅の土地が、一定の要件を満たす場合、小規模宅地等の特例という制度を用いることで、相続税評価額を最大80%(限度面積330㎡)減額することができ、大幅に軽減することができます。
亡くなった方が貸付事業を行っていた土地は、貸付事業用宅地として相続税評価額を最大50%(限度面積200㎡)減額することができます。
⑶ 相続時精算課税制度
そのほか、相続税対策に有効な制度として、相続時精算課税制度があります。
原則として60歳以上の父母または祖父母などから、18歳以上の子または孫などに対し、財産を贈与した場合に選択できる相続時精算課税制度を選択すれば、2500万円まで贈与税がかからず、超えた分も一律で20%の贈与税しかかかりません。
このように、贈与時に贈与税がかからずに財産を移すことができるのがメリットといえます。
また、令和6年1月1日から制度が新しくなり、相続時精算課税制度に年110万円の基礎控除が創設されました。
これによって、年110万円の基礎控除と、2500万円の特別控除を利用することができるようになりました。
相続時には、特別控除の贈与額が相続財産に加算され、相続税が課税されることになります。
この時、既に支払っている贈与税額を差し引くことができます。