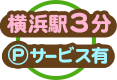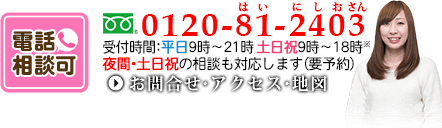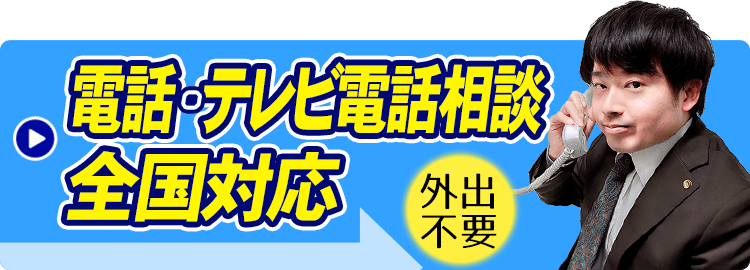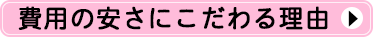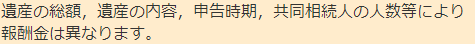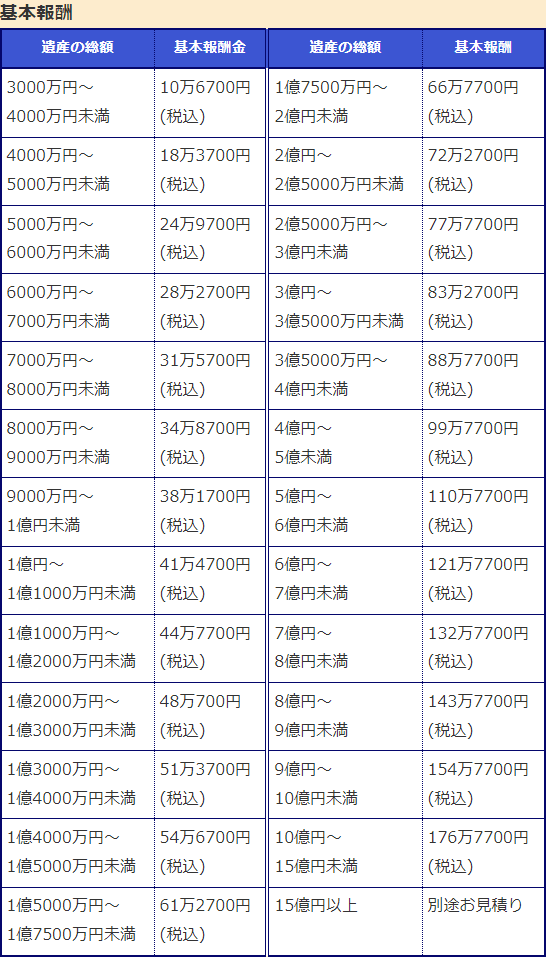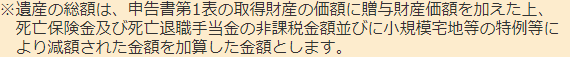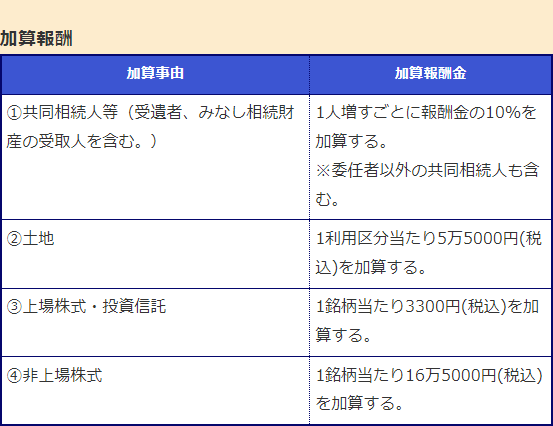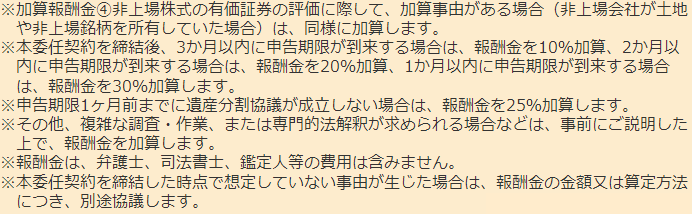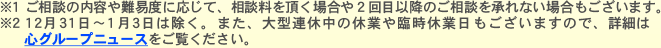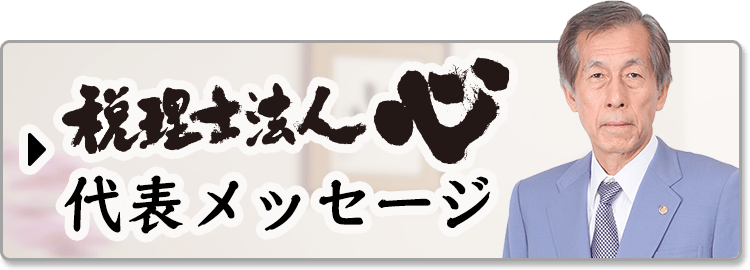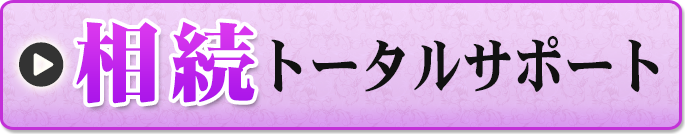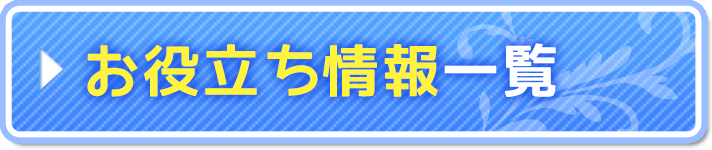「相続税の制度」に関するお役立ち情報
相続税の一括支払いが難しい場合の対応
1 相続税は現金一括払いが原則
相続税は、相続財産を取得した方が、その取得した財産の価額に応じて支払うべき税額を算出することになります。
相続税の申告期限は、通常は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。
相続税申告をするためには、被相続人にどのような相続財産があるかを確定する必要がありますので、その調査もしなければなりません。
この申告期限内に、相続財産を取得した相続人が自分が取得した財産の価額に応じて、それぞれ相続税を納付することになります。
また、相続税は、原則として現金で一括して納付しなければなりません。
そのため、相続財産の構成によっては、相続税を支払うだけの現金が足りない場合も生じてしまいます。
2 現金一括払いができない場合は延納を検討する
申告期限内に金銭で納付することが困難な場合は、その納付を困難とする金額を限度として、担保を提供することにより、延納を申請することができます。
相続税の延納の適用要件は、次のとおりです。
- ① 相続税額が10万円を超えること
- ② 金銭で納付することを困難とする事由があり、かつ、その納付を困難とする金額の範囲内であること。
- ③ 延納税額および利子税の額に相当する担保を提供すること。
- ④ 延納申請に係る相続税の納期限または納付すべき日(延納申請期限)までに、延納申請書に担保提供関係書類を添付して税務署長に提出すること。
①~④の要件について、以下で詳しく解説します。
⑴ ①相続税額が10万円を超えること
各相続人が納税する相続税額が、それぞれ10万円を超えていることが必要です。
延納制度の判定は相続人ごとに行われることに注意が必要です。
相続税が10万円以下の相続人は、延納の申請ができないことになります。
例えば、相続人がAとBの2名、相続税額の合計額が30万円の場合、遺産分割協議の結果、Aの納付する税額が21万円、Bの納付する税額が9万円となった場合には、Aのみが延納の申請ができ、Bはできません。
⑵ ②金銭で納付することを困難とする事由があり、かつ、その納付を困難とする金額の範囲内であること
相続税の支払いが困難な事由があるか否かは、相続により取得した財産だけでなく、相続人が固有に持っている財産を合計しても、なお相続税の納付が困難となる事情が必要です。
延納が認められる金額の計算方法は、以下のとおりです。
延納許可限度額=納付すべき税額-現金納付額
「現金納付額」は、①納期限において有する現金や換価が容易な財産の合計額から②相続人とその親族の3か月分の生活費と③相続人の事業の継続のために当面必要な運転資金を引いた残額で求めることができます。
つまり、相続人の財産をすべて相続税の支払いに使わなければならないわけではなく、生活をしていくうえで必要な分は残しておいても問題はありません。
⑶ ③延納税額および利子税の額に相当する担保を提供すること
延納許可限度額に相当する担保を提供する必要があります。
担保として提供できる財産としては、以下のとおりです。
- ①国債や地方債
- ②社債その他の有価証券で税務署長が確実と認めるもの
- ③土地
- ④建物、立木、登記される船舶などで、保険に附したもの
- ⑤鉄道財団、工場財団など
- ⑥税務署長が確実と認める保証人の保証
なお、延納税額が100万円以下であり、なおかつ延納期間が3年以下の場合は担保の提供は必要ありません。
⑷ ④延納申請に係る相続税の納期限または納付すべき日(延納申請期限)までに、延納申請書に担保提供関係書類を添付して税務署長に提出すること
相続税の納期限は原則として、「被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内」とされています。
例えば、令和7年10月13日に亡くなった場合には、令和8年8月13日が納期限となります。
もし、その期限が土・日・祝日にあたる場合は、その翌営業日が期限になります。
この期限までに延納申請を行う必要があります。
⑸ 延納ができない場合
延納が場合は、物納することができるか検討する必要があります。
3 延納が難しい場合の対応
⑴ 物納が認められるには例外的な場合であり、以下の要件を全て満たしている必要があります。
ア 延納によっても金銭で納付することが不可能であること
物納は延納によっても金銭で納付することが困難な場合に、その困難とする金額を限度として物納の申請をしなければなりません。
イ 物納できる財産から選定されたもので、申請の順位を満たしていること
相続で取得した国内の財産でなければ物納はできません。
また、相続時精算課税制度を使った贈与により取得した財産は物納できません。
ウ 納付期限までに税務署に申請書を提出すること
⑵ 相続税で物納ができる財産には、法定の順位によらなければなりません。
財産の種類は、次の順位(①から⑤の順)によるものとされ、上位から優先的に、物納申請することとなります。
ア 第1順位
① 不動産、船舶、国債証券、地方債証券、上場株式等
② 不動産および上場株式のうち物納劣後財産に該当するもの
イ 第2順位
③ 非上場株式等
④ 非上場株式のうち物納劣後財産に該当するもの
ウ 第3順位
⑤ 動産
⑶ 担保権の設定の登記がされている不動産や、権利の帰属について争いがあるものなど管理や処分に向いていない財産を、管理処分不適格財産といいます。
こうした財産は、物納に不適格な財産として、物納に充てることができません。
⑷ また、地上権、永小作権もしくは耕作権、地役権が設定されている土地など売却等の処分が難しい財産は、物納劣後財産と言われています。
この物納劣後財産は、他に物納に充てるべき適当な財産がある場合は、物納に充てることができません。
4 物納の手続
⑴ 物納申請をする場合、原則として、相続税の納期限または納付すべき日までに物納申請書及び物納手続関係書類を税務署長に提出する必要があります。
ただし、物納申請期限までに物納手続関係書類の提出が難しい場合は、一定の手続を経ることで延長が認められる場合があります。
⑵ 物納の申請に必要な書類は、物納申請書、物納財産目録、物納劣後財産等を物納に充てる理由書、物納手続関係書類などを準備する必要があります。
5 物納申請は条件が厳しく事前準備に時間がかかる
以上で見たとおり、相続税の物納には厳しい条件が課せられており、また申請のための準備にも相応の時間を要することになります。
そのため、相続発生時において納税資金が不足する可能性が高い場合は、不動産等を売却して現金化して納税をすることが一般的です。
仮想通貨は相続税の対象となるのか 神奈川区にお住まいで相続税の相談をお考えの方へ