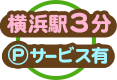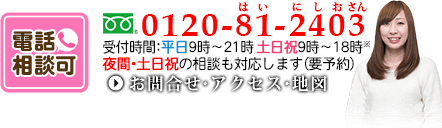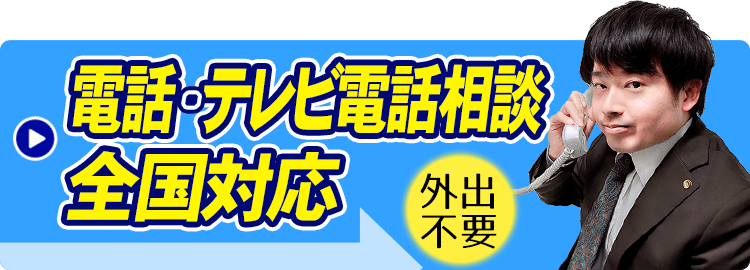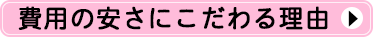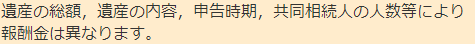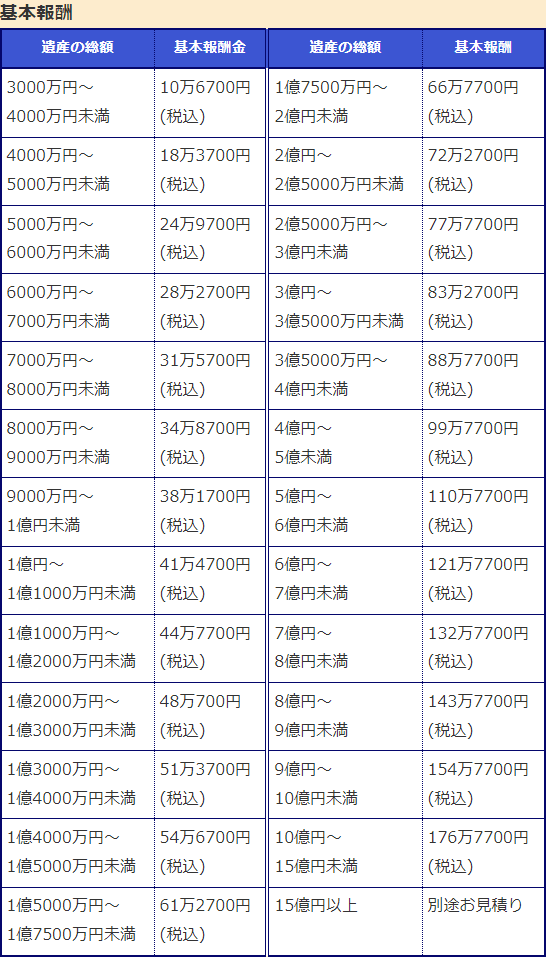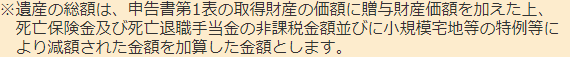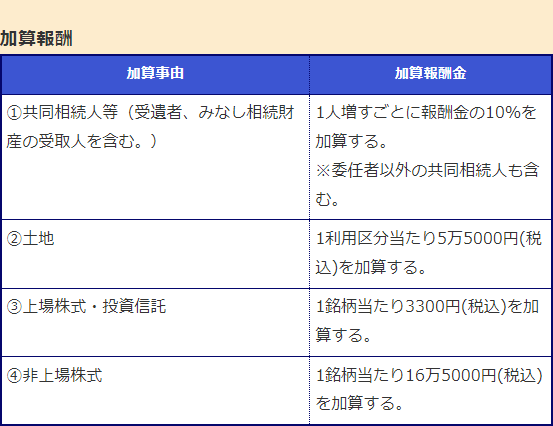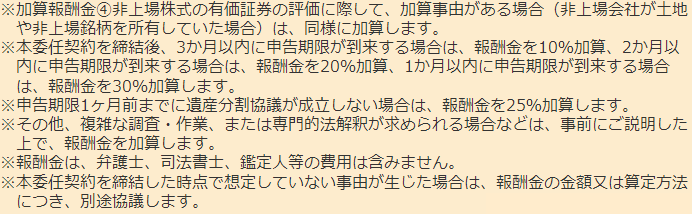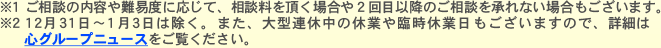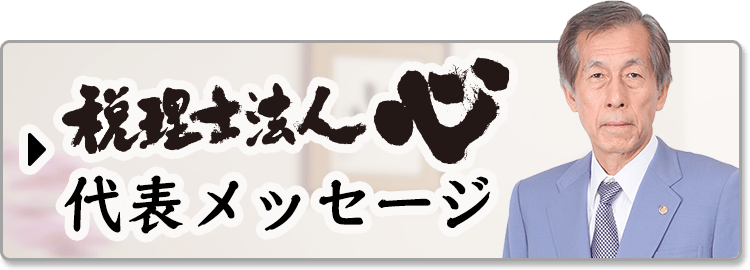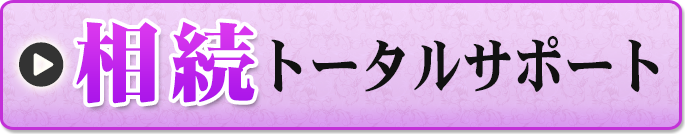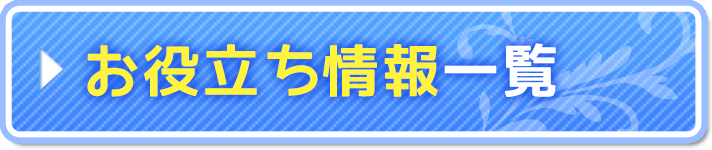「相続税申告」に関するお役立ち情報
期限までに適切に相続税の申告ができないとどうなるか
1 いつまでに相続税申告をしなければならないのか
亡くなった方の相続財産の金額によっては、相続税が発生する場合があります。
まずは、相続税をいつまでに支払わなければならないかという期限の確認から始めましょう。
相続税の申告期限は、通常は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。
申告だけではなく、納税も含めて10か月以内に行わないといけない点には注意が必要です。
なお、申告期限にあたる日が土日祝日の場合は、これらの日の翌日が申告期限になります。
2 相続税の申告が必要かどうか
相続税は、相続財産を取得した方が、その取得した財産の価額に応じて算出されます。
相続税には、基礎控除が定められています。
相続財産が基礎控除の額の範囲内であれば、相続税申告は不要ですし、相続税を納付する必要もありません。
他方、基礎控除額を超える相続財産がある場合は、原則として相続税の申告と納税が必要になります。
相続税の基礎控除は、「3000万円+600万円×法定相続人の人数」とされています。
たとえば、法定相続人が5名の場合の基礎控除は、3000万円+600万円×5名=6000万円になります。
この場合は、相続財産の価額が6000万円を超えた場合に、相続税の申告と納付が必要になります。
3 相続税の申告期限を過ぎてしまった場合のデメリット
相続税の申告期限を過ぎてしまうと、様々なデメリットやペナルティがあります。
申告期限を過ぎた場合、相続税の軽減ができる特例が使えなくなる可能性があります。
さらに、税務署から追徴課税のペナルティが課されるリスクがあります。
具体的には、①延滞税、②無申告加算税、③過少申告加算税、④重加算税といったペナルティが課される可能性があります。
⑴ 延滞税
相続税を定められた期限までに納付しなかった場合に課されるものです。
延滞税は、原則として法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて、利息に相当する金額が自動的に課されます。
なお、延滞税は本税だけを対象として課されるもので、加算税などに対しては課されません。
⑵ 無申告加算税
無申告加算税は、相続税の申告を行わなければならないのに、正当な理由がなく、申告期限までに申告を行わなかった場合に課税されるものです。
なお、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を利用する場合は、仮に相続税が0円になるとしても、申告をしなければなりません。
申告しなかった場合は、特例の適用を受けていない前提で相続財産の総額が計算されることとなり、相続税が課税され、さらに無申告加算税も課税されることとなります。
⑶ 過少申告加算税
相続税の申告はしたものの、税額を少なく申告していた場合に課されるものです。
一度、申告書を提出した後に、新たな財産が発見され、税額を少なく申告していたことが判明した場合でも、税務調査の事前通知がなされる前に自主的に申告すれば、過少申告加算税は課されません。
⑷ 重加算税
相続財産を意図的に隠したり、偽ったりした場合に課税される税です。
4 相続税の申告は早めの準備が大切
このように、相続税の申告期限までに適切に申告・納付しないと様々なデメリットが生じたり、ペナルティを課されたりする危険性があります。
相続が発生した場合は、できるだけ早く相続税の申告期限を確認し、早めに準備をすることをおすすめします。
遺産分割未了の場合の相続税申告 相続税の修正申告が必要なケース