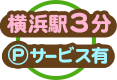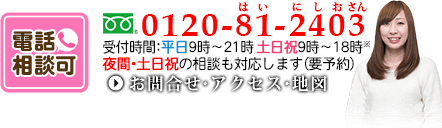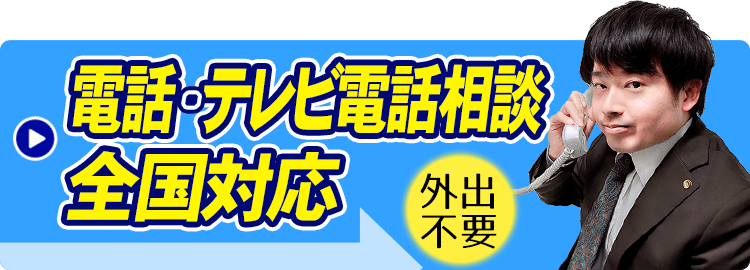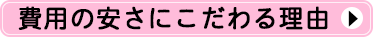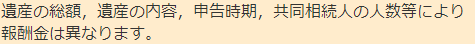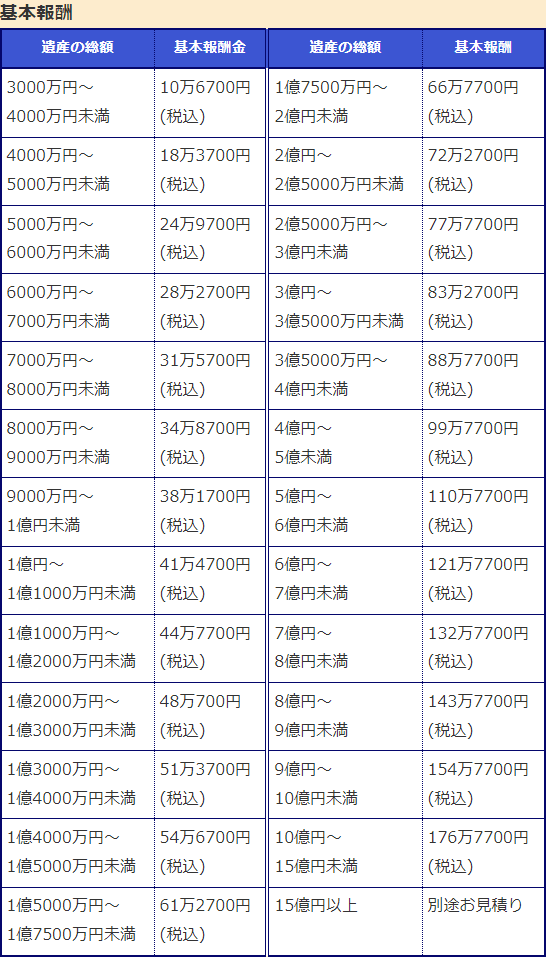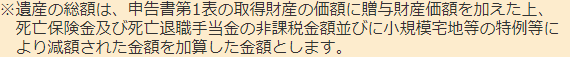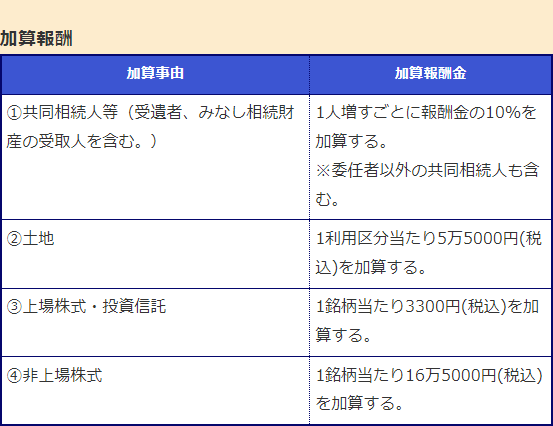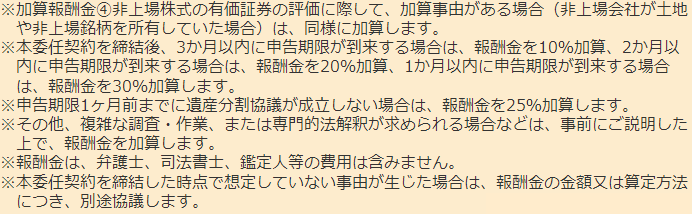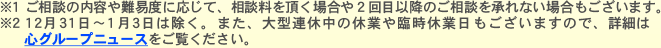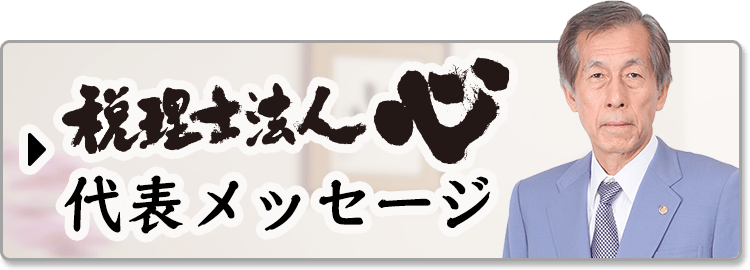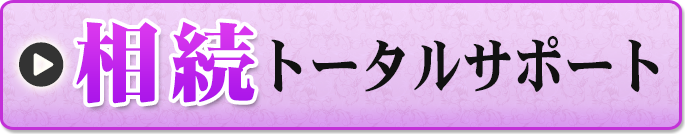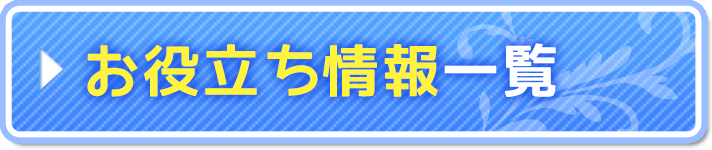「相続税対策」に関するお役立ち情報
養子縁組による相続税対策の注意点
1 相続税申告の基本的なルール
相続税には基礎控除が定められているため、相続財産の総額が基礎控除の額の範囲内であれば、申告が不要であり、相続税を支払う必要もありません。
他方、基礎控除の額を超える財産がある場合、原則として相続税の申告と納税が必要になります。
相続税の基礎控除額は、「3000万円+600万円×法定相続人の人数」で計算します。
この計算式を見ればお分かりのように、法定相続人が1人増えれば、600万円の基礎控除額が増えるということになります。
2 養子縁組をすることで基礎控除額が増えます
養子縁組というのは、血縁関係がない人とも親子関係を発生させる制度をいいます。
養子縁組をすることで、養子は実子と同じように養親の法定相続人となりますので、相続権を有することになります。
養子縁組を行って法定相続人を増やすことによって、相続税の基礎控除額が増えるため、この点が相続税対策としてメリットがあることになります。
しかし、後から述べるように、注意点もあります。
3 養子縁組をすることで生命保険や死亡退職金の非課税枠が増えます
死亡保険金や死亡退職金にも非課税枠があります。
死亡保険金や死亡退職金の非課税枠は、「500万円×法定相続人の人数」で計算します。
養子縁組を行って法定相続人を増やすことによって、相続税の計算において、死亡保険金や死亡退職金の非課税枠が増えますので、この点が相続税対策としてメリットがあることになります。
しかし、こちらも後から述べるように、注意点があります。
4 養子縁組で法定相続人として数えられる人数には制限があります
養子縁組をすることで基礎控除額が増えたり、死亡保険金や死亡退職金の非課税枠が増えたりするのですが、無限に人数を増やせるわけではありません。
相続税法上では、養子を法定相続人として数えることができる人数には制限がかけられています。
被相続人に実子がいる場合は、養子が法定相続人としてカウントされるのは1名だけです。
また、被相続人に実子がいない場合には、養子2名までが法定相続人として認められることになっています。
養子を無限に増やして相続税対策ができるわけではないことに注意が必要です。
その他にも、全くの他人を養子とすることで、他の相続人と遺産分割協議で揉める可能性が高まることもあるので、その点にも注意が必要です。
相続税対策として遺言を作成するメリット 不動産を活用した相続税対策のメリット