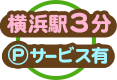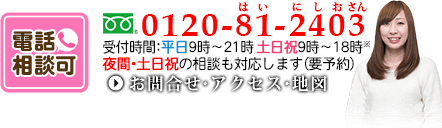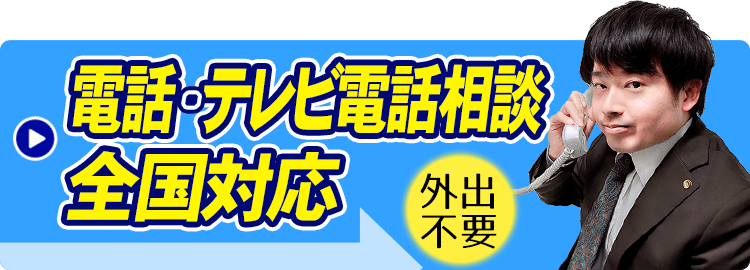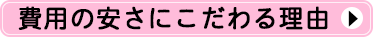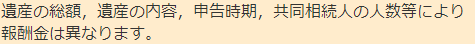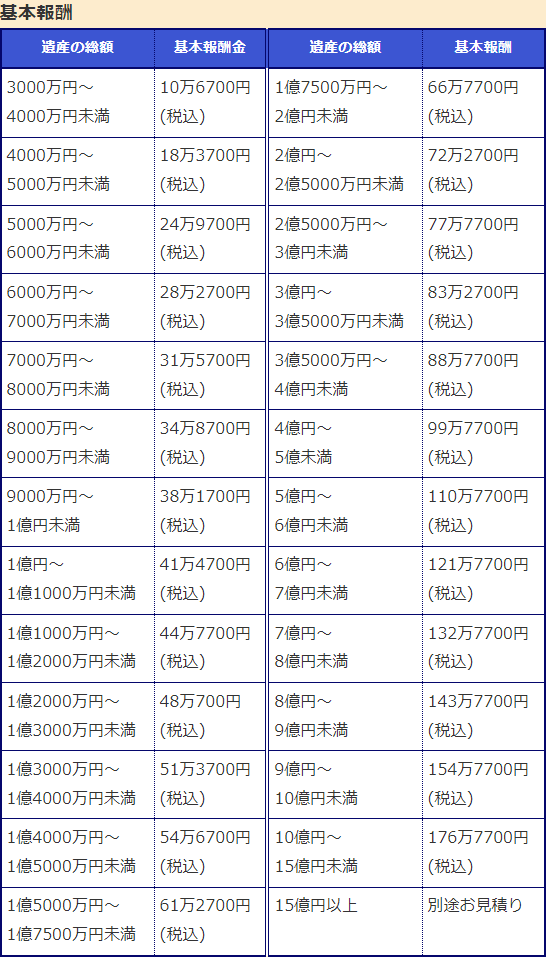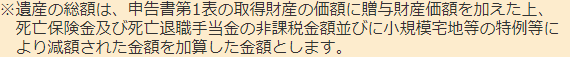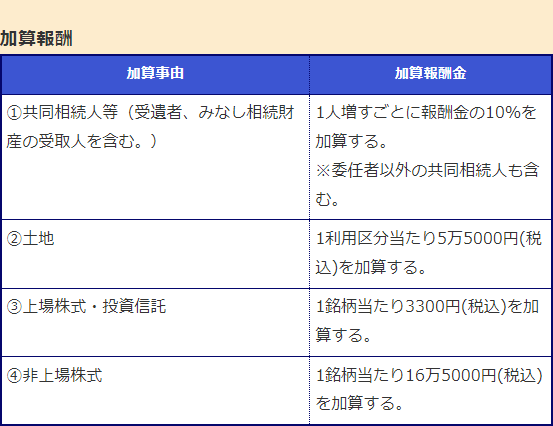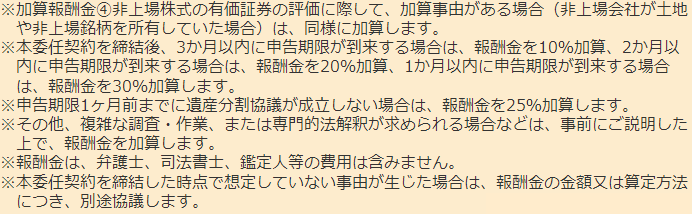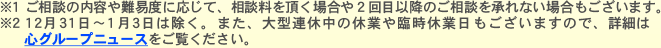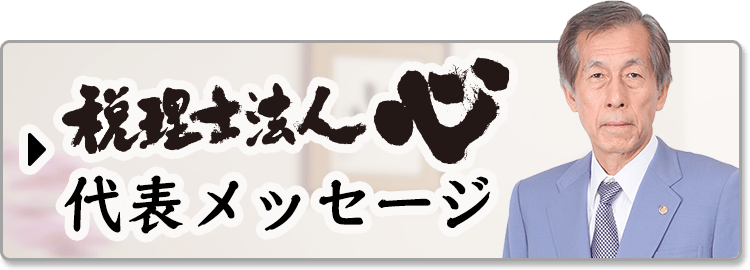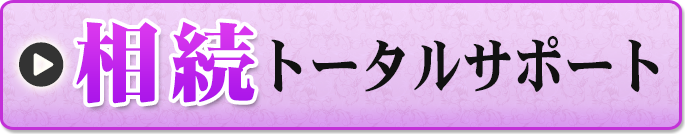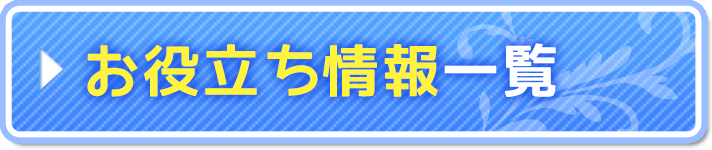「相続税対策」に関するお役立ち情報
相続税対策として遺言を作成するメリット
1 遺言を作成するメリット
遺言にはいくつかの種類がありますが、代表的なものとして、自筆証書遺言と公正証書遺言の2つが挙げられます。
自筆証書遺言は手書きの遺言のこといい、公正証書遺言は公証役場で作成する遺言のことをいいます。
遺言を作成するメリットは色々ありますが、遺言は被相続人の最終意思として法的に尊重されるため、法定相続分よりも優先されることになっています。
したがって、遺言を作成した場合の最大のメリットは、原則として遺産分割を行う必要がなくなる点にあります。
また、法的に有効な遺言書を作成しておけば、原則として、預貯金の解約手続、株式の名義変更手続、不動産の名義変更手続などをスムーズに行うことができます。
さらに、遺言で遺言執行者を指定することで、遺言執行者が遺言の内容を実現するため、よりスムーズに手続きを進めることができるようになります。
2 遺言を作成しないことのデメリット
遺言が無い場合は、相続人全員で遺産分割をしなければなりません。
遺言が無く、遺産分割を行わなければならない場合、相続税との関係において以下のようなデメリットがあります。
⑴ 相続税の申告・納付期限との関係
亡くなった方の相続財産の金額によっては、相続税が発生する場合があります。
基礎控除額を超える相続財産がある場合は、原則として相続税の申告と納税が必要になります。
相続税の申告と納税には、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内という期限があります。
この期限は、原則として延長することができません。
一方、遺産分割のための話合いは、必ずしも円滑にまとまるとは限りません。
相続人同士で紛争になってしまい、話合いで解決に至ることができない場合は、遺産分割調停・審判という裁判手続によって解決することになります。
この話合いや調停は長引くこともあり、その場合は解決まで1年以上かかることもよくあります。
このように、遺産分割について合意に至らないまま、相続税の申告期限を過ぎてしまうこともあります。
この場合、遺産から相続税を納めることができず、相続人が自らの財産から相続税を支払わなければならないという事態に陥るおそれがあります。
⑵ 相続税を減額するための制度との関係
申告期限までに遺産分割が完了していないと、当初の申告において、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例といった、相続税を減額するための制度を利用することができません。
遺産未分割の状態で相続税の申告・納付を行い、後から税金の還付を受ける方法もあります。
しかし、いったんは減額されていない金額の税金を納付しなければならない上に、還付のための手間もかかります。
⑶ 相続税の納税資金との関係
申告期限までに遺産分割が完了していない場合、相続財産の解約、払戻をすることができません。
そのため、⑴でも触れたように、相続税を相続人の自己資金から納付しなければならなくなります。
この時、十分な自己資金が無く、相続税を納付することができなかった場合には、本税の他に延滞税等のペナルティが課されることとなってしまいます。
この点も、遺言が無い場合のデメリットの1つであるといえます。
3 遺言を作成することによる相続税対策
遺言を作成しておけば、遺産分割協議や調停・審判を行うまでもなく、最初から遺産分割が完了している状態を実現することができます。
そのため、上記のような、遺産分割が相続税の申告・納付に間に合わないリスクや、納税資金が不足するリスクを避けることが可能です。
相続税の円滑な申告・納付を実現するためにも、あらかじめ遺言を作成しておくことをおすすめします。