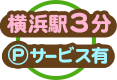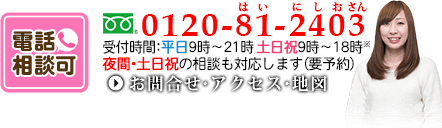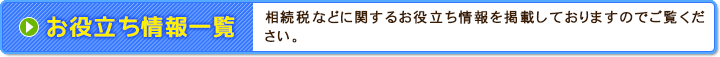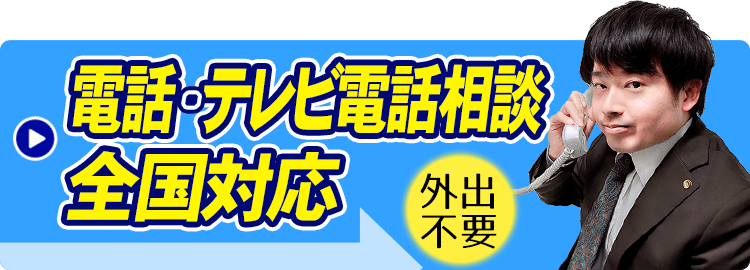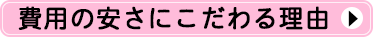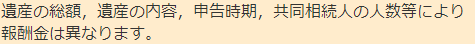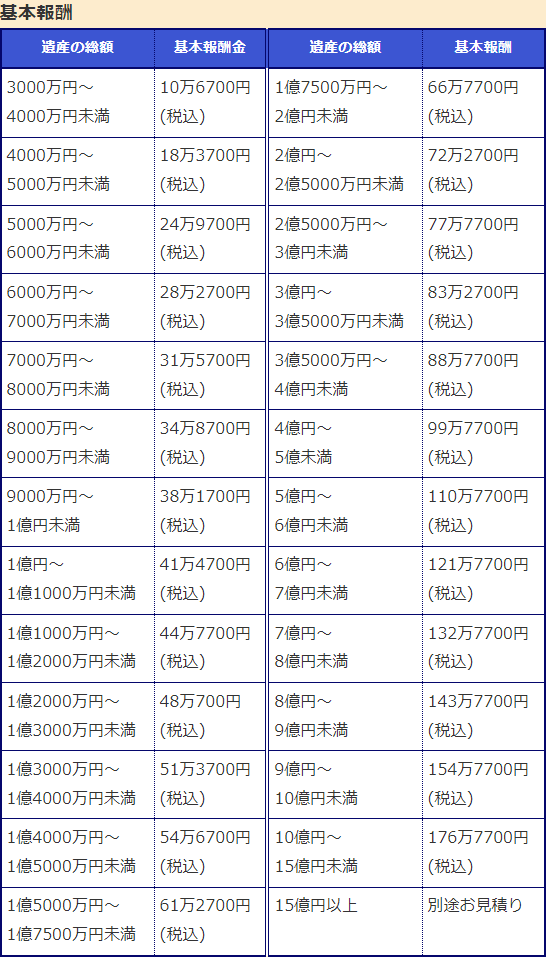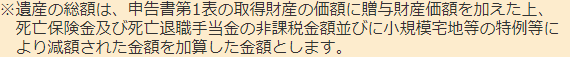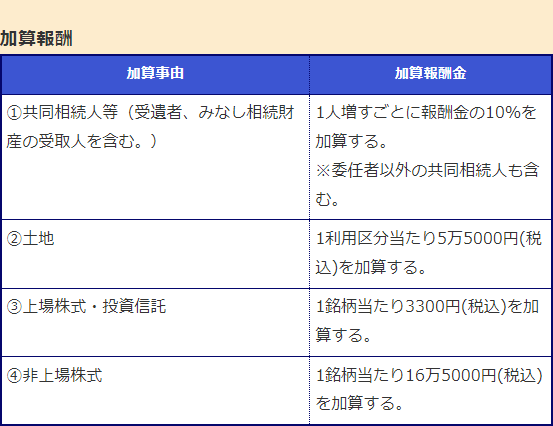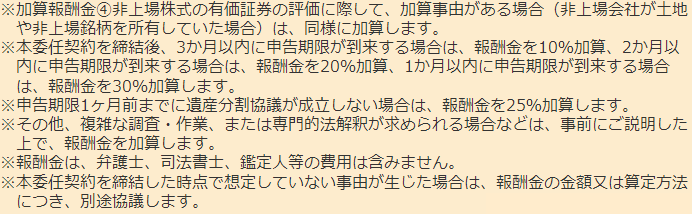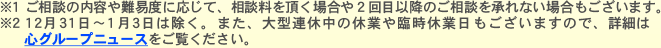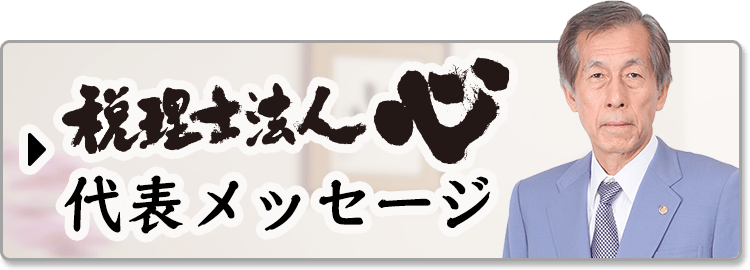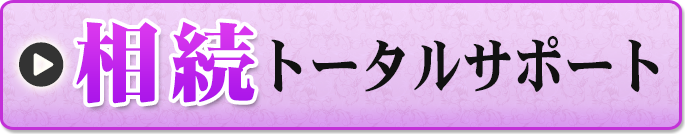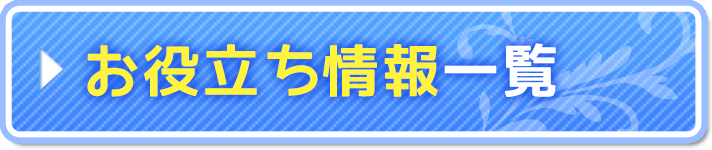生命保険での相続税対策に関するQ&A
生命保険に加入することが相続税対策になる場合がありますか?
生前贈与と同様に、生命保険に加入することも有効な相続税対策になりえます。
生命保険に加入することによって、相続税の金額を減らすことができる場合があります。
また、生命保険は納税資金を確保する手段にもなります。
なぜ生命保険への加入が相続税対策になるのでしょうか?
相続税とは、相続により財産を取得した場合に、その取得した相続財産に課される税金のことをいいます。
相続税は、被相続人が亡くなった時点で有していた財産の総額を計算し、債務と葬儀費用を差し引いた金額について課税されます。
つまり、生命保険に入ることによって課税の対象となる財産が減ると、相続税額が低くなるということになります。
生命保険と相続税にはこのような関係がありますので、生命保険は相続税対策になると言われています。
死亡保険金に相続税の非課税枠はありますか?
被相続人が被保険者となっている死亡保険金は、みなし相続財産として相続税がかかります。
もっとも、死亡保険金には非課税枠というものがあります。
死亡保険金を相続人が受取る場合、法定相続人の数×500万円までは、相続税が課されません。
たとえば相続人の人数が3人であった場合、500万円×3人=1500万円までの死亡保険金には、相続税が課されません。
この法定相続人の数の中には、相続放棄した人も含まれます。
このように、非課税枠の範囲内の死亡保険金であれば、相続税が課税されないことになります。
例えば、相続人として子どもが3人いて、相続財産として1億円の預金がある場合、預金の一部を生命保険に代えることで、相続税額を225万円程度減額することができる可能性があります。
その他に相続税申告の際に生命保険がもたらすメリットはありますか?
相続税は、原則として現金一括で納付しなければなりません。
相続財産の中に価値が高い不動産があるものの、現金や預貯金はほとんど無かったために、相続税の納税資金が足りなくなってしまい、納税資金を手当てするために泣く泣く不動産を売却しなければならなくなったというケースもありえます。
また、遺産の中の預貯金から相続税を納付しようと考えていたものの、遺産分割協議がまとまらない等の理由から預貯金を引き出すことができず、相続税の納税資金が賄えないというケースもありえます。
このような場合に備えて、あらかじめ生命保険に加入しておき、相続人を保険金受取人に指定しておけば、死亡保険金は相続人固有の財産として、現金で支払われます。
この死亡保険金で相続税を納付することができるため、不動産を売却しなければならないような事態を避けることができるというメリットもあります。
生命保険以外で相続税の非課税枠を利用できる保険はありますか?
保険の中ですと、生命保険だけが非課税枠を利用できます。
そのため、相続税対策になる保険は生命保険だけです。
建物共済や医療保険、損害保険や一部の個人年金保険などは基本的に相続税対策にはなりませんので、注意が必要です。
相続人以外で生命保険の非課税枠を利用できる人はいますか?
死亡保険金の受取人が相続人の場合に限って、非課税枠を利用することができます。
そのため、死亡保険金の受取人が相続人の配偶者や子になっている場合や、受取人である相続人が相続放棄をした場合には、非課税枠を利用することができず、相続税対策にはなりませんので注意が必要です。
死亡保険金本体以外に非課税限度額の対象となるものはありますか?
死亡保険金本体以外に、一定の金額(500万円×法定相続人数)までは相続税が課税されないものとしては、配当金、割戻金、前納保険料、未経過保険料があります。
なお、保険金の請求後、実際に保険金の支払いがなされるまでの間に、保険金に利息が付して支払いがなされることがあります。
この利息は、保険金請求後に発生したものであり、被相続人の死亡後に発生したものではありませんので、相続税の課税対象になりません。
相続税申告における未払保険料の扱いはどうなるでしょうか?
保険会社から死亡保険金が支払われる際、保険料の未払分が差し引かれて支払われることがあります。
この場合、本来の死亡保険金の額から未払保険料を差し引いた額、つまり、保険金の受取人が現実に受け取った金額がみなし相続財産と扱われることになり、非課税限度額の対象になります。
本来の死亡保険金の額がみなし相続財産と扱われて非課税限度額の対象となり、未払保険料の額が債務控除の対象となるという話もありますが、これはよくある誤りですので、注意が必要です。
生前贈与の失敗事例に関するQ&A 贈与税と相続税に関するQ&A