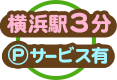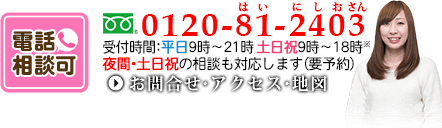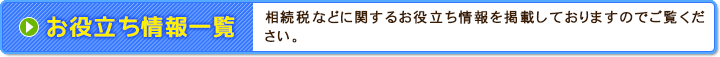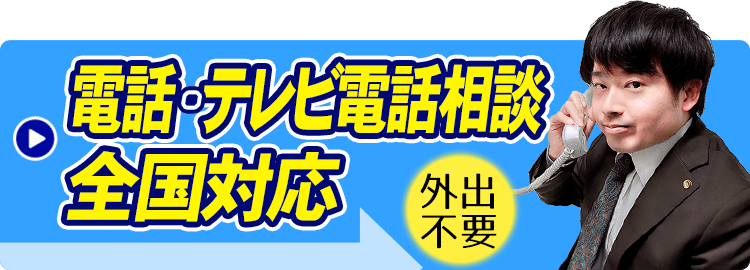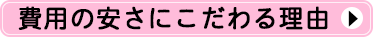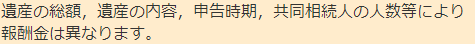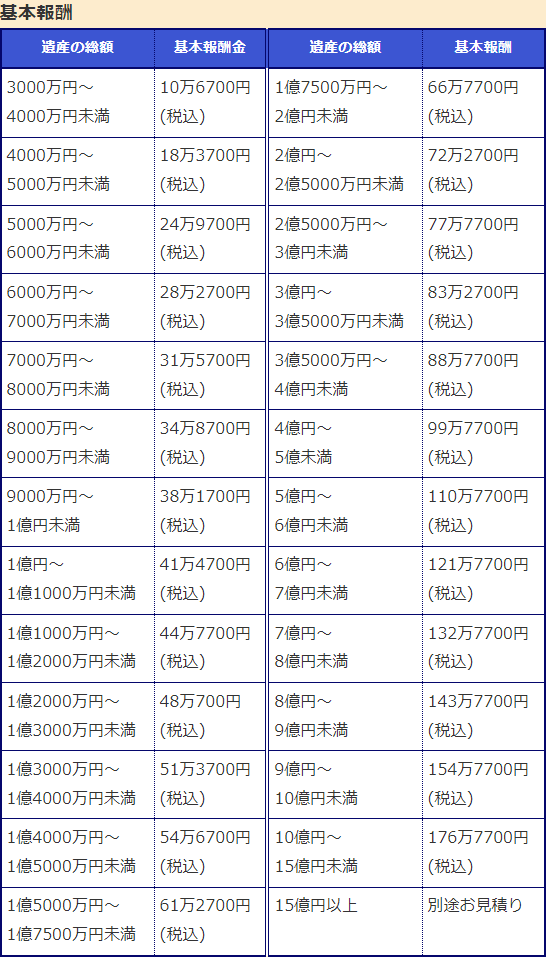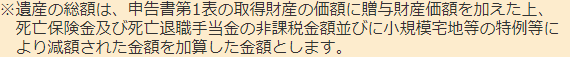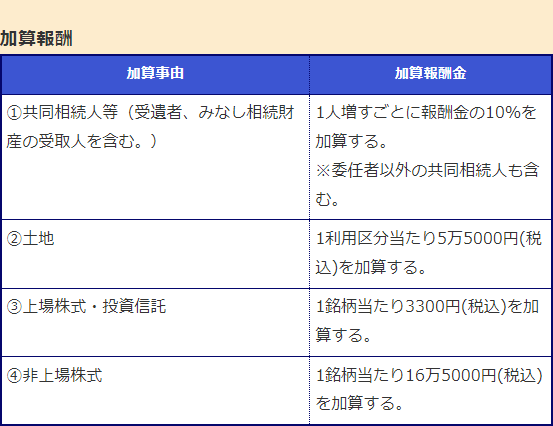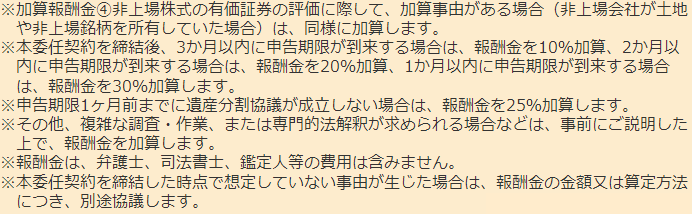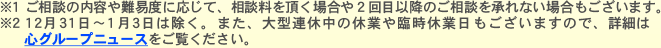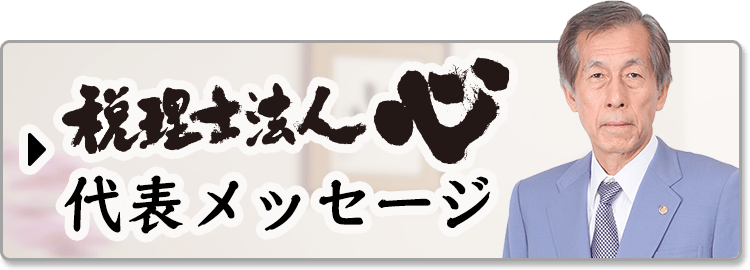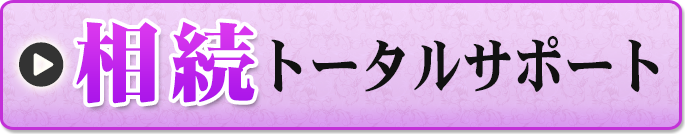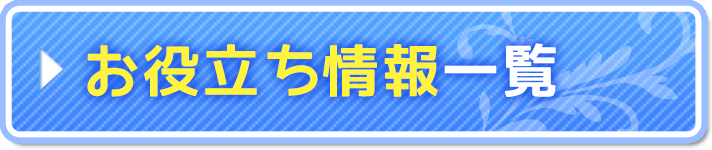生前贈与の失敗事例に関するQ&A
生前贈与とはなんですか?
生前贈与とは、被相続人が生前に相続人や第三者と行う贈与契約のことをいいます。
生前贈与も契約ですので、当事者双方の合意が必要になります。
つまり、贈与者はあげたという意思表示をしていること、受贈者はもらったという認識があることが必要です。
生前贈与でよくある失敗事例はなんですか?
⑴ 相続発生前の一定期間内になされた贈与があるケース
相続発生前3年以内(令和6年1月1日以後に贈与により取得した財産については段階的に相続発生前7年に延長)の贈与は、原則として相続税の課税対象となるため、これを忘れていると以下のような失敗をする可能性があります。
被相続人が亡くなり、被相続人の家族は遺産の調査をしたところ、基礎控除の範囲を超える相続財産があったため、相続税の申告と納税を行いました。
しかし、後日、税務署から連絡があり、追加で相続税を支払うよう求められました。
税務署によると、税務調査の結果、相続発生前の一定期間内に相続人に多額の贈与がされていた形跡があるが、この贈与金額が申告されていないとのことでした。
このようなケースだと、財産を少ないと見積もって申告したことになるため、「過少申告加算税」が課されてしまいます。
過少申告加算税の税額は、増えた分の差額×10%という計算式で求められます。
ただし、増えた分の差税額のうち、当初に申告した税金または50万円のうち大きい方の金額を超過する部分があるときには、その税率が15%になります。
⑵ 暦年贈与が否定されるケース
他にもよくある失敗事例としては、贈与税がかからないように年間110万円以下の生前贈与(暦年贈与)をしていたのに、税務署から暦年贈与と認められずに否認されてしまい、相続税を課されてしまうケースです。
父が、子に生前贈与をして遺産総額を減らし、相続税を軽くすることができると考えて、子と贈与契約を結ぶことなく、毎年決まった日に子名義の口座に入金をしていた場合が典型的なケースです。
このような場合、受贈者にもらったという認識が無いため、税務署から贈与と認められずに否認されてしまうことがあります。
贈与契約しても、通帳の管理を親がしていた場合はどうなりますか?
贈与契約の事実があるということも重要ですが、受贈者がもらった財産を自分自身で管理しているかという実態も重要になります。
父が子に贈与をしたのに、父が通帳や印鑑を管理しており、子はその口座のお金を1回も使ったことがないというような場合には、受贈者である子が財産管理をしていないと判断される可能性があるため、注意が必要です。
贈与契約の証拠がない場合は不利になりますか?
税務署からチェックが入った場合、仮に贈与契約をしていたとしても、証拠が無ければ贈与を否認されてしまう可能性があります。
そのため、贈与契約をした証拠や、受贈者が財産管理をしていた証拠などを収集・保管しておくことも重要です。
一括の贈与とみなされてしまう場合はありますか?
以下のようなケースでは、一括の贈与とみなされてしまう可能性があります。
例えば、親が暦年贈与の非課税枠の範囲内である110万円までであれば贈与税が課せられないという点に着目し、子に毎年110万円ずつ、10年かけて1100万円を贈与したとします。
毎年同じ時期に同じ金額を長期に渡って贈与した場合には、税務署は、最初から1100万円を贈与する意図があったのではないかと考えることがあります。
そのような場合には、1100万円の贈与として贈与税が課せられる可能性があるため注意が必要です。
どんなものが相続税の課税の対象となりますか? 生命保険での相続税対策に関するQ&A